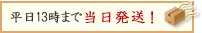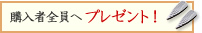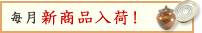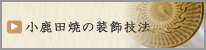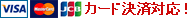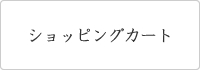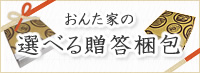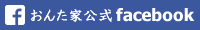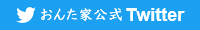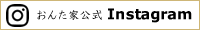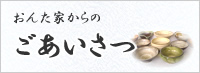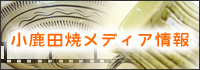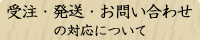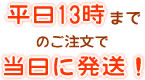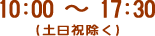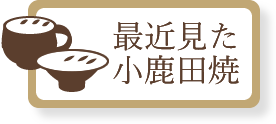TOP >小鹿田焼の歴史|小鹿田焼の作業工程|小鹿田焼について 小鹿田焼の装飾技法
小鹿田焼について~小鹿田焼の装飾技法~
シンプルだけど奥深い。伝統の焼ものを日々のくらしへ。
江戸徳川幕府の直轄地「天領日田」。
おんた焼の装飾技法
小鹿田焼の技法~飛び鉋(とびかんな)~

飛び鉋とは、かめや壺の胴部、皿の内面に施された、帯状のリズミカルな模様である。
特徴的な技法の一つで、蹴りろくろを回しながら、生乾きの化粧土に湾曲し先のとがった鋼片を当て、当て方によって生じる鋼のバウンドによって器物の表面に刻みを入れます。
素朴で可愛らしいのにどこか力強く奥が深いのが特徴。
飛び鉋の商品はこちら
小鹿田焼の技法~打ち刷毛目(うちはけめ)~

打ち刷毛目とは、かめや壺の胴部、皿の内面に施された、帯状や菊の花びらを思わせる柔らかな模様です。
半乾きの素地の上にたっぷりと白土を塗り、それが固まる前に刷毛を当てて模様を表しますが、ろくろの回転と刷毛の当て方の強弱により濃淡の模様が表れます。
主に大皿をはじめ、皿類に施します。
打ち刷毛目の商品はこちら
小鹿田焼の技法~打ち掛け~

打ち掛けとは、釉薬を入れたひしゃくを使い、軽く水をまくような動作で部分的に勢いよく打ちつけるように掛ける手法です。
半月状の模様が生じ、即興的な面白さがあります。
数種の釉薬を別々に壺のあちこちに打ち掛ける事もあり、単純な模様でありながら、変化も楽しめます。
主として茶壺類に装飾されますが、他の技法と併せて一部に施されることが多いです。
打ち掛けの商品はこちら
小鹿田焼の技法~流し掛け~

流し掛けとは、スポイドや先の細いひしゃくに入れた釉薬を、長めの線上に流して表した模様です。
蓋付きの壺や半胴の甕類に多く施されていますが、連続した線の集積はシンプルでありながら、直線から受ける快い強さを感じます。
流し掛けの商品はこちら